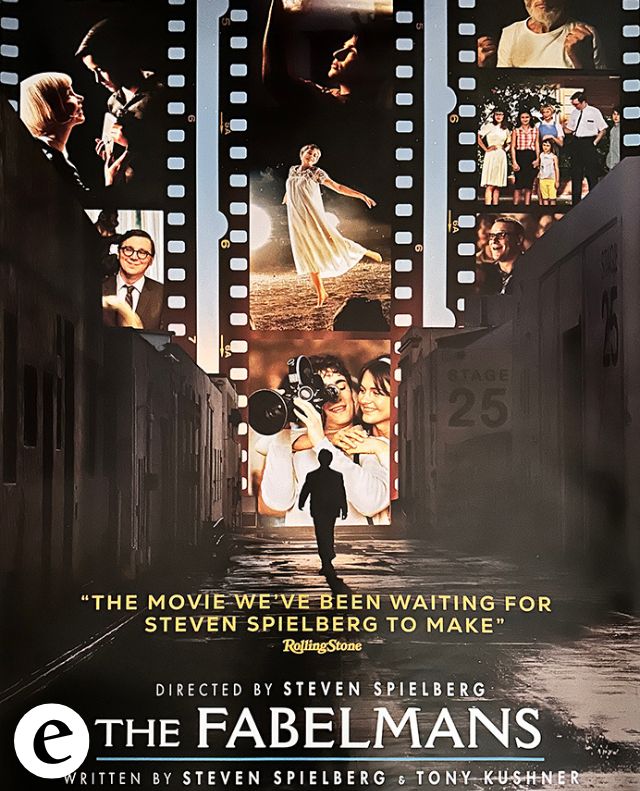<公式>
ストーリー:今から50年後くらいの未来、LA中心部で核爆発が起こる。AIの攻撃と判断した米政府、西側諸国はAIの開発や使用を禁じる。いっぽうアジア諸国はAIとの共存を選び、両陣営は抗争状態になっていた。元特殊部隊のジョシュア(ジョン・デヴィッド・ワシントン)はアジアに潜入し、究極の開発者”クリエイター”の暗殺に向かう。そこで彼が出会ったのは兵器でもある少女型AI、アルフィーだった....
『GODZILLA』『Rogue One/Star Wars Story』などの監督、ギャレス・エドワーズの監督・脚本作。専門家たちの声は「いま、オリジナル脚本で、シリーズものじゃないSF大作が作られたこと自体尊い」。賞賛のトーンとしては少し物悲しい。そういうものなのか、現代。「インディーズ的制作方法を大作に融合させた」というのもある。必ずでるのが、コンシューマービデオカメラSONY FX3で少人数クルーがアジア各地の風景をゲリラ的に撮影して、画面のベースに使っているという話。
ストーリーはそこまで独自という感じのものじゃなかった。「人類vsAI」というおなじみの対立は、「〈人間〉の境界は何か」とか「人間とAIとのコミュニケーションには〈心〉が介在するのか(または人間が勝手に相手の反応アルゴリズムに〈心〉を投影してしまうのか)」みたいな機微がテーマになりがちだけど、本作ではそこまで踏み込まない。アクションとエモーションが主体の物語だから思考実験タイプじゃないのだ。
前者は古典『ブレードランナー』の中心的テーマだし『her』『エクス・マキナ』『アフター・ヤン』それに新しい『ブレードランナー2049』は後者を描いている。本作でのAIは人型ロボットに人工知能が組み込まれた個体だ。一部は見るからにロボットで、かといって『Chappie』みたいな機械っぽいロボットに人間性を感じさせる演出でもない(ロボットのエモーショナルなシーンは1つだけあった)。この辺りのAI+ロボットの心や記憶や人との関係はNetflixアニメの『PLUTO』の方がだいぶ丁寧に描いていた(8話ドラマだからキャパシティが違うけど)。
登場人物として機能するのは〈シミュラント〉と呼ばれる、人間の姿をコピーしたロボットだ。『エクス・マキナ』の初期段階みたいに後頭部はわかりやすくメカ化されている。表情は人間と同じように感情表現できる。助演の子役マデリン・ユナ・ボイルズや渡辺謙はこれらだ。メカ的な制約は時々あるが、反応は普通の人間と変わらない。それどころかボイルズ演じるアルフィーは後半になると単なるいたいけな少女となり、いかにも泣いて欲しいところで涙を見せたりして、急速によくある大人と子供ストーリーの雰囲気になっていく。
(c)2023 20th century studios via imdb
僕がいいなと思ったのは物語世界のデザインの方だ。ハイテック化するアジアと保守的な西側、という物語の対立軸も若干どうかと思うし、「アジア」のざっくりとしすぎたまとめ具合(ベトナムの農村風景や粗末な木造建築の漁村、唐突な仏教寺院風テンプル、東京的なカオスなハイテク都市...)も少々素朴すぎる世界観にも見える、というところはあるけど、映像としてはアジアンミクスチャー料理みたいな新鮮さはあった。
監督が『アキラ』も参照作にあげているように、そしてデザインソースに80〜90年代のSONYデザインをあげているように、プロダクションは既視感ありつつぼくらの見たかったメカのかっこよさを実現している。基地の扉一枚、ローカルの車両、雑魚キャラのAI ロボもそれなりの説得力ある造形だ。
ちなみにあらためてSONYのデザインを見ると、エモーション的要素が入らないハイテクデザインのキレの良さみたいなものを感じる。機能を形にするところで踏み止まり、よけいな面やラインを付け加えないのだ。AppleはSONY 以上にミニマルなデザインを創るけれど、SONY より少し分かりやすくエモーションに訴える造形を入れてくる気がする。
もっとも秀逸なのは超高高度にいる巨大な空中要塞〈ノマド〉だ。攻撃対象を上空からスキャンし、その後圧倒的な破壊力を上空から浴びせる。物語の世界観にすごく効いている。上空の支配者イメージ、最近だと『 NOPE』のUFOがあったね。衛星軌道からの攻撃は『アキラ』にでてくるSOL。マンガでいうと『横浜買い出し紀行』という名作SFに上空から地上を観察する巨大飛行体が描かれていた。あと『未来少年コナン』のギガントにも形態的には近い。この無慈悲な存在が米国コングロマリットの象徴みたいに物語に君臨するのだ。
ところで〈シミュラント〉という人間そっくりAIロボの名称。人間の突出した顔認識力で、3つの点がいい具合に並んでいると嬰児でも顔だと認識する〈シミュラクラ現象〉を思わせる。いろんなパターンの中に顔を見いだす〈パレイドリア〉という能力の一つだ。
監督がいうにはシミュラントのデザインを考えるとき、顔と首の前側がないと人は生身っぽく感じてくれない(顔だけだとお面のように見られる)と分かって首の人体部分を残したそうだ。よく顔写真だけ切り抜いて親しみやすさ狙いのイラストみたいのが作られる(TV局の番宣素材とか)けれど、あれも首部分まで入れると急に生々しくなるということだろか。
◾️アド・アストラ
<公式>
こちらは特にAIと人間、というような話じゃない。人間同士の、というより父子の葛藤が宇宙スケールで展開するのだ。SF的描写は『ザ・クリエイター』と比べると今の宇宙技術の延長みたいなところがある。舞台は太陽系で、火星に基地があり、冥王星まで行くのが人類の到達点、くらいの世界だ。
出てくるガジェットも、実在の宇宙船や月面車両や、そんなものを思わせる、機能100%みたいなデザインだ。一番インパクトがあったのは、成層圏はるか上までの高さがあるタワーのシーンだ。事故が起こると人々は真っ直ぐ地上に落下していったから、重力圏は脱出していないんだろう。地上と人工衛星軌道をつなぐ宇宙エレベーターは技術的にそんなに夢物語じゃないという。タワーのイメージは新鮮だった。
そんな感じでブラッド・ピットもこの上なく抑えめの演技で、ストーリーも抑制的に続くのだが、途中のハラハラシーンで割とトンデモ風展開になってしまうので作り手がどこまでリアルに描こうとしているのかが見えづらくなっているきらいはある。